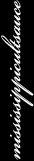20067.29
下りゆくエスカレーター
何度か目が覚めたはずだ。起きようと思えば起きられただろう。一日の睡眠時間としては十分すぎるほど眠ったはずだが、それでも起きられなかったのは、昨夜の深酒のせいかもしれない。そうして何度目かに目が覚めたとき、はじめは耳鳴りのように、しかし次第にはっきりと、遠くに聞こえる祭り囃子か、サンタクロースのそりのような、鈴の音が聞こえてきたのだ。そして上半身を起こす間もなく、大きな白い骨組みが私の前に現れた。
「乗れ」と、そう聞こえたようだった。
その大きな白骨の馬車は、部屋の虚空から、ふいに現れた。
純白に輝く、複雑に入り組んだ骨の構造体。一頭の馬、それに跨る骸骨は金色の手綱を握り、光り輝く綱は馬の頭骨の隙間をくぐっている。馬の胸元から伸びた数本の太い綱は後ろに繋がれた車両に結ばれており、風のない部屋の中で奇妙に軽く波打っている。車両もまた何かの骨で組まれており、屋根はなく、妙に傾斜した座席の背後に、羽のような飾りが左右に大きく突き出している。そしてその飾りの両側に、宙に浮くようにして、大きな骨の車輪がゆっくりと回っている。長い骨が蜘蛛の巣のように組み合わさってできたその輪の縁に、まるで時計の文字盤のように並んだ十二の炎。それはひとつずつ順番に、勢いを増しては衰え、時を刻むように回っていた。
「乗れ」と、再び聞こえた。
白骨の馭者は巨大な頭蓋骨をこちらに向けて、ぽっかり開いた眼窩に縁取られた深い闇から私を見据えた。私は恐る恐る起きあがり、手前に突き出た一本の骨を握った。既に私の体の半分は、抗えない力に動かされているようだった。残りの半分も、ぼんやりとして動かす気にはなれなかった。なんとなく、自分がどうなるかがわかった。骨の足場に、右足をかけた。不思議とはっきりしてきた頭で、さっきまで自分の寝ていたところを振り返ると、枕元の鉢植えに、ずいぶん長いあいだ水をやっていないことに気がついた。
水を、と思った。しかし、どうしてだろうか、そのとき、私は残る左足も、既に踏み出していたのだ。
- « カメラ・アナグリフの沈黙
- 海に降る雪 »
trackback URL: