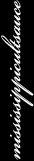20067.28
カメラ・アナグリフの沈黙
出かけるまで少し時間があったので、爪を切っていたんだが、途中で切れなくなった。涙がポトポト止まらなくなって、指がそれ以上動かなくなった。たぶん何かが詰まっているのだと思い、中をのぞいてみると、ははあ、なるほど、先の方に何か縦に長いものが挟まっていて、それが上板の動きを止めているのだ。白っぽくて切った爪のようでもあるが、やけに均一な太さで真一文字につっかえているので、もっと別の何かのようにも見える。試しに爪楊枝でつついてみることにした。退屈気味の来客に、手品のひとつやふたつ披露する機会もあるだろうと思って取っておいた爪楊枝だ。思えば爪楊枝という言葉にも爪という字が入っている。組んだ太ももにポタポタと、藍のジーンズに青を染め出す涙の一粒は、ほてった体を少しでも冷やすだろうか。ツイツイとつついてみても、これがまたなかなかどうして微動だにしない。よほどのジャストサイズではまっているのだろう。楊枝の方がつぶれて使い物にならなくなった。カーテンから漏れる黄色い陽はくしゃくしゃになったベッドシーツを浮き彫りにする。温もりにふくれた羽布団は、冷たくなった今もそのままの形で残っている。こうなったら力任せに、床においた爪切りを、足で思いっきり踏んでみることにした。こんなに分厚い金属の骨組みが、少しぐらい乱暴に扱ったからといって、挫けてしまうことはないだろう。喉がかわいた。飲み物はあったかな。割れてしまったグラスの替えも、もういらなくなってしまった。さあ、乾坤一擲、思い切りが肝心、いや、それよりも、ちょっと待った。さっきからなんだ。おれの回想に横から茶々を入れるやつは誰だ。グラスなんて割れた覚えはないぞ。どうしてだろう、椅子に座っていられない。床にうずくまって、乾いたカーペットのにおいを感じる。そもそもなんだ。家でジーパンなんて履くやつがあるもんか。この蒸し暑いのに。底から眺めた部屋は広角に歪んで見え、重力は倍増しでのしかかる。押しつぶされて沁み出したものが、目じりを流れて耳へと落ちる。さあ、ままよ、踏むぞ、爪切りを踏むんだ、見ていろ、おれの勝ちだ、見ていろ、何か音が聞こえる。ガスの漏れるような音がする。体が動かない。喉がかわく。夕立でも降り出したのかもしれない。洗濯物。干したままになってたっけ。いくつかの時代をまたいでも、何も変わらないものがあって、僕はなるべくそれを、見ないようにしてきたのに。
trackback URL: