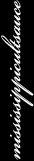20067.16
スルスエイの狩り場から
砂浜にたどり着いたのは、私の記憶の方が、少しだけ正しかったということだ。松林に垂れかかる夕暮れ時が、道行く人をみな串刺しにしている。あんなに、灰色の蒸気にむせかえる埠頭、斜めに焼き付いた朱色の光線、跳ね返る血のプリズム。
私の記憶の方が、少しだけ正しかったということだ。魚はビニール袋を飛び出す。浮き袋をめいっぱい膨らまして、焼けたアスファルトに落ちる。拍子を取って、景気よく、跳ねて、踊って、私のズボンに裾から潜り込む。
太陽は磯辺に溶け落ち、海水を吸ってふやける。ブヨブヨにのびたオレンジの光に、汚いウミドリがくちばしを寄せる。薄い貝殻は砂をまぶし、波に呑まれるのを待っている。雲が戯れるあそこで、遠い岬が鼻高々に歌う。
砂浜を越える頃に、夕立のようなにおいがする。木立を抜ける海風が、ぐるりとねじれては勢いづく。硬い松葉を震わして、磔の街路に流れ込む。私も、少しは正しかったということだ。防波堤の影に、倒れ込むようにして、最後の一閃がのびる。ひと泡吹いて、ひときわ燃えるようで、辺りは一瞬冴え渡り、いつのまにか暗くなる。
- « 椀に夕日
- アニマル・トーキング »
trackback URL: