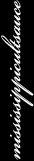20062.26
トイ・チューブの思い出
ジョニーが帰ってきた。ジョニーは遠いどこかに忘れてきてしまったたくさんのことを、ひとつひとつ思い出そうとしながら、アラスカの青すぎる空の下を歩いていた。渓谷は彼を待っていた。数え切れない年月を数えながら、風は彼の歌を憶えていた。沼湖は彼の吸った空気を、今もその輝くおもてに湛えていた。湖岸に立ち並ぶ古木は、彼の足跡を優しく隠していた。彼は大きな倒木に腰をかけ、静かに涙を流した。しかし彼は思い出せなかったのだ。あまりにも長い忍苦と硝煙の日々が、彼の無垢の神経をぼろぼろの燃えかすに変えてしまっていた。鳥が鳴いていた。彼には聞き覚えのない鳴き声だった。ジョニーはおもむろに立ち上がり、果てしなく遠く高く突き抜けたアラスカの空を仰いだ。太陽はじきに南中し、様々の生き物たちがその光を浴びて歌いはじめるだろう。ジョニーはひとりふらふらと、何かに誘われるように、暗い森の中へと迷い込んでいった。強い極北の光をも遮る巨木の足もとを、ジョニーはよろめきながら進んでいった。光は絡み合った針葉樹に乱反射し、彼の顔に薄暗くまとわりついた。湿った大気が充満していた。むせかえる苔のにおい、饐えたキノコのにおい、ずっと昔から閉じこめられた太古の原生林のにおいだった。ジョニーの足音に合わせて、羊歯の胞子が薄い光を透かして舞った。ジョニーは大洋に浮かんだ無人の船のように、何か抗えぬ力に流されるように進んでいった。そのとき、ふと、辺りのしじまを破るように、こーん……、という澄んだ高音が森全体を貫いた。ジョニーは音の出所を探した。再び、こーん……、と、そしてまた、追いかけるように、こーん……、と響いた。ジョニーはぼんやりとしていた頭を瞬時に統一し、精神を目と耳にのみ集中し、しばらく辺りを見回した後、薄暗い森の奥に、然るべき一点を見つけた。ジョニーの鋭く差し向けられた視線の先には、何か不可思議な、人間ほどの大きさをした生き物が、巨木の影で動いていた。こーん……、と、再び同じ音が鳴り響いた。ジョニーは恐る恐るその何者かに近づいた。ジョニーは確信していた。それは確かにジョニーの知っているあらゆる生き物とも違っていた。ジョニーはゆっくりと距離をつめていった。それはジョニーに気付かず、ずっと同じ動作を繰り返しているようだった。ジョニーは見た。それは確かに生きていた。そして、それは、人間だった、いや、人間のような形をした、木で作られた、木樵だった。木で作られた木樵が、人間と変わらぬ動作で、大きな斧を巨木に振り下ろしていたのだ。まるで命を吹き込まれたかのように、生き生きとして。こーん……、こーん……、と、木の木樵は斧を振り下ろし続けた。木は次第にぐらつきはじめ、倒れるのは時間の問題だった。木樵は、ジョニーがすぐ傍らに近寄っても、まるで意に介さないように木を切り続けた。それは、確かに木で出来ていた。どこからみても木に違いなかった。しかしそれは、まぎれもなく木樵だった。そして、疑いなく生きていたのだ。本当に、あれは、なんだったんだろうと、ジョニーは今でもふいにあの日のことを思い出す。目を閉じると、こーん……、こーん……、と、あの不思議な木樵が斧を振り下ろす音が、すぐそこに聞こえてくる。なくしてしまった若き日の思い出を、深い深い湖の底に探すソナーのように、こーん……、こーん……、と、木樵の斧はいつまでも彼の鼓膜に振り下ろされ続けるのだろう。
- « 優しい顔
- あの素晴らしい愛をもう二度 »
trackback URL: