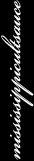20068.13
サボテンのスライス・サラダ
ときどきピタピタと頬に感じる雨。空の指先が僕に触れる。
葬式はまさに今の天気にピッタリだった。彼女の葬式は、静かに進んでいった。沈み込んでしまいそうな時間の水面を、神父の抑揚の効いた声だけが、飛び石のように跳ねていた。それから僕は涙を流していた。
彼女を入れた棺に、土が投げられてゆく。僕が最初にかけてあげたかった。そして最後にも僕が。
参列者たちが、湿った芝生を踏む音が耳ざわりだ。何もかもが鮮やかに見える。そして今は、何もかもが目ざわりだ。
彼女の脱いだ服のにおいを、僕はすぐに思い出せる。ちょうど今の空気のような、湿った街を包んだような。そんなとき、僕はすぐに窓を開ける。
神父が本を開き、ふたたび閉じた。黒いヴェールが、むせるように息づいた。
僕は何もしゃべらない。式は滑らかに続いていく。雲は西からやってきて、彼女の白い体をくるんでしまう。彼女に、今日の空を見せてあげたかった。羊の毛並みのような銀色の空、月のような太陽。雨に滲んだ、最後の最後の光。
悲しいことなんてどこにもない。神父は両手を仰いでいる。本はどこかに隠してしまった。傘がなくて良かった。神様、僕の涙は下水に流れればいい。パンツを履いていない僕に、言えることはそれだけだ。
trackback URL: