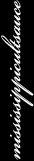20067.18
驚くべき光の中へ その2
エミールは頭を抱えた。こんな雨じゃ手紙を出しに行けない。夜ももう長くはない。
暗闇の中で、彼は抱えた頭を、くしゃくしゃのベッドにほうった。ひどい雨の音がする。鼓膜がぬれちゃいそうだ。ああ、いっそこの部屋を、どこか流氷の浮かぶそばにでも、流し去ってくれればいいのに。エミールは組んだ足をぴょんと上げて、湿ったシーツに転がした。雨漏りかもしれない。天井の隅が、灰色に濁って見える。ちょっとした、光の加減かもしれない。エミールは足の指でカーテンの端をつまんで、器用にめくった。薄い窓ガラスの表面に、四角く切り取られた夜。真っ暗闇の向こうからでもなんとなく光はやってくるらしく、隙間から差し込んだ夜の火は、暗い天井にぼおっと広がって、さっきまであった雨漏りの色を、いつのまにか消してしまっていた。
- « アニマル・トーキング
- 土気色のヴィーナス »
trackback URL: