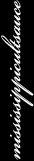20067.14
椀に夕日
キルギリスが倒産したので、彼女らはどこか他のところで花を売るか、男のところに種を売るか、郷里に戻って油を売るか、しなければならなかった。一度染みついた色はなかなか落ちない。それでも三分の一くらいは、すぐにまたその辺に種をこぼし、ふたたび花が咲くのを待つことになった。ある女、フランソワと呼ばれていた女は、前の持ち主に特別に気に入られていたこともあって、その界隈で飛ぶ鳥を落としていた下げ底の城、フウルミに種を落とすことになった。フウルミでは女も男もよく働いた。その名の通り全く働き者の集まりだった。夜の蝶は飛ばず、死して屍をさらわれ、そして最後に腹を肥やすのが彼らだった。彼らは一種の熱病に潤んでいた。熱にうかされ五体をすり減らし、すり減らしては熱を生む。それは大きな火柱となって、街の夜を赤々と照らし出した。そして日々のとろ火に煮え切らずにいたフランソワの灯心も、その火の粉に中てられたのだろう、烈火のごとく燃えたのだった。
フウルミが倒産したので、彼女らはどこか他のところで売る物を売らなければならなかった。しかし働き者だった彼女らはみんな、たった一人フランソワを残して、すぐにパラパラとどこかに種を蒔いた。フランソワはというと、火種を残す心に打ち水し、輝きすぎていたせいで、彼らは何も見えないんだわ、でも楽しかった、満足していたわ、生きる喜びと言ってもよかった、幸せだった、とにかく、あぶなかったわ、と言って、残った貯金でとりあえずバイオリンを弾いて暮らした。
- « パルス・ライダー
- スルスエイの狩り場から »
trackback URL: