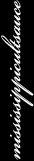20066.29
眠りの謎 その5
もう一度雲を読む。薄雲の隠した虚空の底を見透かしてみる。露を結んだ冬のグラスに、沈んだ氷を探すように。指先で触れるとあらわれる。風はどちらに流れているだろうか。雲が動けばわかる。風の吹かないよく晴れた日には、雲はずっと決まったところに影を落とす。嵐のあとの膿んだ地面に、小さな雲と、もっと小さな太陽が、眠っている私が起きないくらいに、ずっとひとつところに傘を差し立てる。そういう日は、光と影の境を、一度だけ渡ってみせる。影から光に入るとき、私は熱帯のトカゲのように、メラメラと脈打つ体をジッとくるめて、満ちゆく体液の波間に浮かぶ一粒の毒となる。影に飛び込む私は、一艘のスペースシャトルに違いない。硬い金属の体を、無重力の中に見失う。進んでいるのか、漂っているのか、知らない。薄雲の切れない日も、上空には速い風があって、ぞくぞくと雲は流れてゆく。たまには千切れた雲のひとつが、私のところまで降りてこないかと思うが、私は若い。まだ私は待つことができる。妙に明るい。眠気が差してきた。今が何時か知らないが、そろそろ昼寝にいい頃かもしれない。ああ、手が届きそうだ。瞳のすぐ先にあるのに、死んだ両手には遠い。白んだ空には雲間さえ見えない。しかし私は、何一つ余計なものはない。この空の下で眠るのがすきだ。
trackback URL: