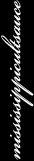20065.17
サーフィン・オン・シロッコ
理髪師は頭を抱えた。
おとといから客が一人も入っていない。今月は何人切っただろう。片手を指折り、余ってしまう。先の予約も一件しか入っていない。それも九日後だ。だめだ。家族で首をくくらなければいけない。いけない。そんなことでは。なんとかして客を呼び込まなければ。客さえ入れば、ああ、一日に二人でも入ってくれれば、どうにかしのいでいける。三人入ればどうだろう。ずいぶん楽になる。例えばもし、五人、いや、十人入ったとしたら、そうしたら、それがずっと続けば、こんな崩れかけた店さっさと閉めて、表通りにもっと立派なやつをこしらえてやる。そうだ。それがいい。十人、二十人入ればいい。どれだけでも働いてやる。朝早くから開けて、日が暮れても、朝が来るまでずっとウェルカムだ。どうだ。できないことはないだろう。時間はたっぷりある。そうだ。やってできないことはあるまい。体力さえもてばいい。ふふふ。そしたらどうだ。こんな汚い街、いつでも捨ててやる。そうだ。おれは出て行くぞ。夢のような南国の暮らしが、すぐそこに見えるぞ。ああ、手が届きそうだ。でもまだだ。まだ待てよ。ふふふ。おれには腕はないが、足はある。自慢の足だ。ふふふ。丈夫な太腿、かしわのようなふくらはぎ、しなやかな足首、柔軟な爪先がある。いつでも歩いていくぞ。エメラルドグリーンの海よ。体力には自信があるんだ。どうだ。ふふふ。ふふふ……。
理髪師は嬉々として身悶えた。と拍子に理容椅子のスイッチが入った。椅子はゆっくりと傾きだし、やがてほぼ水平になった。
trackback URL: