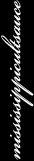20065.8
シーズ・ザ・サン
どうしたところで無駄かもしれない。絶望的な問題だ。なんとしても帰らなければならない。私の眼前で、シャトルは灰黒い煙を一定に吐きながら、冷えた尾翼を虚空に逆立てて永遠に沈黙している。帰らなければ、いけないと、そう思えば思うほど、私の頭の深奥で、無数に繋がれた神経の腕々が力無く下ろされていくのがわかった。宇宙のさいはてに一人取り残され、このまま塵と消え行くのだろうか。それはどこか私の知らないところで、私の知らない誰かの作った、何か遠大な仕掛けのように思えた。
しかし私は帰らなければいけない。帰らなければいけない、たぶん今ごろ私の愛は、しらしらと揺れる光の狭間で、朝もやにつつまれ眠っているだろう。ああ、結局そうして、最後までいいそびれてしまう。
trackback URL: