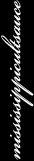20064.28
スリーピング・カラーズ
こどもがお湯にあごまでつかって、百まで数えさせられるみたいに、僕はもうずいぶん昔から、星を数えずにはいられない性分だった。夕暮れの薄闇に、一番星がたったひとつ淡い光を浮かべていたら、どんなわずかな光も逃すまいとして、すっかり闇の落ちたあとも時の経つのを忘れて星探しをしてしまうのだ。だから運悪く満天の星空に巡り会ったりしたら、誰かが力づくで僕を空から引っぺがすまで、延々と、恐らく疲労か飢えかに倒れるまで、ひたすら星を数え続けてしまうのだ。そしてあるとき、すっかり疲れ切っていた僕はとうとう医者に相談することを決め、処方箋を書いてもらった。そうしてしばらくしたら、いつのまにか、僕は蒼々と星降る夜にひとり打ち捨てられても、何も感じないようになった。もやもやと胸をかき乱すあの焦燥は消えてしまった。星は、夜空は、こんなにきれいだったのか、と思った。それはあまりにも尊い発見のように思えた。ある日、僕はふと、また昔のように、星を数えてみようという気になった。ひとつ、ふたつ、みっつ、よっつ、得体の知れない思いが喉を満たしてくると、いつつ、むっつ、ななつ、それから、じゅうさん、じゅうよん、じゅうご、じゅうろく、でも、それ以上は無理だった。何度やっても無駄だった。僕はもう、星を二十も数えることができなくなってしまっていた。送電線の振動する音がやたらと耳のそばで聞こえる。僕は家の鍵をバッグに探しながら、どういうわけか震えが止まらなかったのだ。
- « 35度のキャスケット
- 凱旋また凱旋 »
trackback URL: