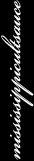20064.23
詐欺師、楽園へゆく
大きな石柱の陰に立ち止まって、彼はふと、やってきた道をかえりみた。ぼうぼうと茂った草むらが、太陽を隠すまでに伸び広がっている。踏んだはずの地面はすでに青々と覆い隠され、ふたたび辿り行くのも叶わないだろう。彼は石柱にもたれて、静かに育ち行く草の隙間を、白銀にぬめる空を見た。どうしてだろう。不思議な気持ちだ。見知らぬ土地をひとりさまよい、道程を失い、冷たい石とからだを分け合う孤独の球心を、澄んだ空気が触れていく。もはや進むべき道も失い、踏むべき足裏もさびついてしまったが、濡れたこころの襞のまに、乾いた風が抜けていく。草むらは今にも天を跨ぎ、白日を盗んで闇に隠すだろう。彼は柱の元に座り込み、やがて寝転んだ。長い道程は捨ててしまったのだ、と彼は思った。此方と彼方をつなぐ橋には、多くの人手と労力を無駄にする。拡がりすぎた都市はただひとつの意志も支えられない。ばらまかれた骨片のそれぞれが、熱にうずいて震えている。そうして茫漠の星霜に溶け残ったわずかばかりの彼自身が、この小さな草造りの巣にふたたび結晶するのかもしれない。彼は目を閉じている。暗闇の中で、まるで息を止めたように動かないので、眠っているのかもしれない。眠っているのなら、たった今、彼のはるか頭上を、二羽のカモメが飛んで行った、その夢を見ているのかもしれない。
trackback URL: