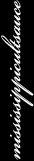20063.17
天才の条件
いつからか、その部屋には蟹がある。見たところ平凡な温泉旅館の一室のようだ。可もなく不可もない、誰もがどこかで目にしたことがあるような部屋だが、狭いかと言えばそうでもなく、畳も障子も艶っぽく、心ばかりのようではあるが縁側も設けられ、存外居心地は悪くなさそうだ、と、そんな評価を受けそうな部屋である。窓からは夜が透けて見え、まんべんなく紅葉した楓が、縁の中まで枝を伸ばしている。楓に寄り添うようにして、小さな石灯籠がぼんやりと闇の中に浮かんで見える。部屋の中は明るい。灯りの下で、蟹はトゲトゲの脚を編み籠から豪快にはみ出させて、部屋の中心に鎮座している。誰かが手をつけた形跡は窺われない。並べられた小皿の類もきれいなまま残っているところを見ると、これから食事が始まろうとする、まさにその直前のようだ。しかし部屋には誰もいない。もうずっと、ここには誰もいない。蟹は朱色の顔をかしげて、大きな甲羅の隙間から、たっぷりの味噌をさも自慢気に覗かせていたはずだが、しかしそれも今では、長い時間の末に、墨色の干し葡萄のようになってしまって、殻の縁にこっそりとへばりついている。綿毛のように見えるのは黴だろうか。よく見ると皿の中の液体、ポン酢か何かのタレのようだが、その液面には細かい埃がアメンボのように集まって、全体を三分の二くらい覆っている。じっさい、タレももう僅かしか残っていない。皿のへりが茶色く変色しているのを見ると、半分くらい蒸発してしまったようだ。蟹の甲羅も乾いている。ぎざぎざになった尖端には黴がくっついて、頭をかしげたまま、長い脚を宙ぶらりんにして座っている。その目玉は灰色に濁っている。いつからか、そのようにして、そこには蟹があり、どのようなわけか、その部屋には、もうずっと誰もいない。
trackback URL: